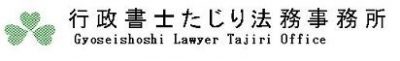当事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

成年後見に関する専門的な知識と福祉に関する豊富な交流・サポート経験を活かして、高齢者や障害者等へのサービスを行っています。
後見といっても、法定後見もあれば任意後見もあります。場合によっては、民事信託の方が最適かもしれませんし、遺言書で済むときもあります。
常に本人の生活環境や心身の状態、本人を含めたご家族の希望に沿った最適な対応策をご提案します。

当事務所は、生きていれば誰もが直面する遺言・相続や消費活動等に伴う契約上の疑問や要求など個人に対するサポートだけでなく、30年間のIT業界におけるビジネス経験と法律に関する知識の両面から、起業を志す人に対する最適な種類の法人設立、融資・助成金や許認可申請、契約書の作成・チェック、著作権など知的資産に関するアドバイスなど、法人設立後の運営につきましても専門的にアドバイスします。
主として、人手不足に悩んでいる中小企業や介護事業所等への支援策として、外国人技能実習生の受入など在留資格許可申請における申請取次業務も行っています。
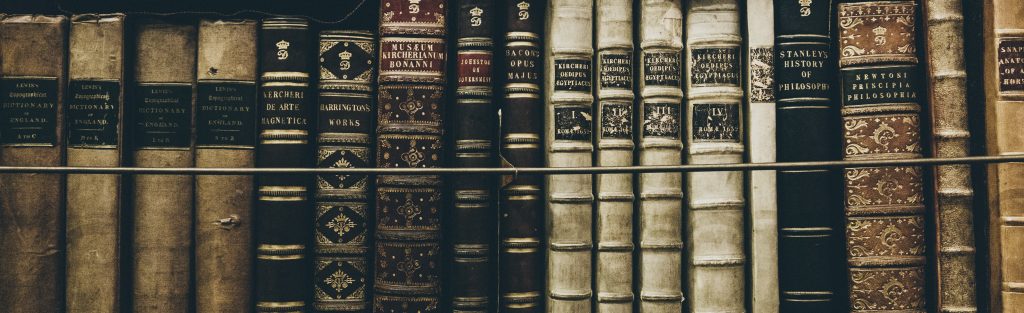
主なサービス内容

後見制度のことがよく理解できないので、使いたくても使えないという声をよく耳にします。そんな方に、後見制度全般について、具体的に、分かりやすくご説明します。是非ご相談ください

近くに親族もいない人や身寄りもない人が認知症になってしまったときは、家庭裁判所に法定後見の申立てが必要です。手続き等で分からないことがありましたら、ご相談ください。

見守り契約に始まり、身上監護や預貯金等の財産管理を行う委任契約及び任意後見契約、更には、死後の事務処理を行う死後事務委任契約まで、分かりやすくご説明します。是非ご相談ください。

本人の死亡若しくは判断力が低下した後、本人の財産を信頼できる親族に託して、残された配偶者や障害を持った子供等が何不自由なく暮らしていけるようにしたいと考えていらっしゃる方、是非ご相談ください

終活の知識はあっても肝心の遺言書の作成方法が分からないで困っている方。相続手続きで途方に暮れている方、是非ご相談ください。 遺言書の作成支援並びに遺言執行や遺産分割協議書の作成など相続手続きについてサポートします。

通信販売などによる消費活動上のドラブル、結婚相談所への入会やオーディション合格後の専門学校への入学に伴う契約上のトラブルも増加しています。 このようなご相談並びにクーリングオフのための内容証明郵便の作成、送信などのお手伝いをしております。 是非ご相談ください。

株式会社や合同会社といった営利法人並びに一般法人や事業協同組合といった非営利活動法人の設立や定款変更に加えて、法人の解散・清算についてもサポートしています。 是非、ご相談ください。

個人事業主や法人の運営に不可欠な秘密保持契約や売買契約、販売代理店契約、事業の買収契約など様々な契約書の作成やアドバイスを行っています。また、特に著作権においては、アパレルに関する著作権を専門に扱っております。 是非ご相談ください。

古物営業や貨物利用運送事業、無店舗型風俗営業、建設業等事業を営む上で官公庁の許可を必要とするものがたくさんあります。提出書類の作成から資料収集、提出代理までサポートします。是非ご相談ください。

在留許可申請
外国人の在留資格証明書の取得等を行う申請取次業務を行っています。外国人を採用したいと考えていらっしゃる方は、是非ご相談ください。